
『アメリカの不良娘・ベッキー 』Vol.7――「ラブレターと毛深い男と、夜のトレーラーハウス」――
煙草を買いに出る、ただそれだけのはずだった。
けれど、僕がベッキーに手紙を渡してからの数時間は、まさに「青春の大脱線」だった。
金髪のベッキーと二人きりのディナー。ラブレターの手渡し。彼女の“旦那”の存在。そしてその旦那が今、「jail(刑務所)」にいるという衝撃の事実……。
あまりの展開に頭が真っ白になった僕は、「ちょっと煙草を買いに行ってくる」と言ってから2時間、まったく言い訳も思いつかないまま、トレーラーハウスへ車を走らせていた。
言い訳を考えようとすればするほど、頭にこびりついて離れない言葉があった。
「Oh, it’s my husband…」
この一言が脳内リピートされすぎて、思考停止に陥っていた。刑務所って。三人って。
なんで笑ってるんだベッキー……。
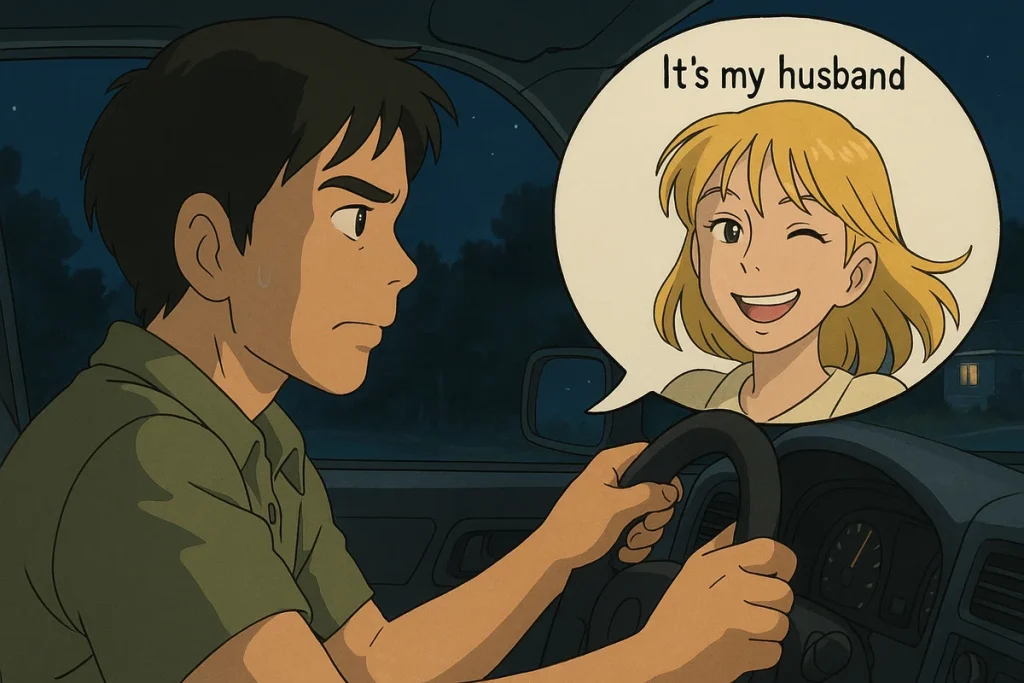
もうどうにでもなれと思い、「え~い! ままよ!」と車のドアを勢いよく閉め、僕は何食わぬ顔でトレーラーハウスのドアを開けた。
「ただいま~」
――返事なし。
恐る恐るリビングに入ると、そこには誰の姿もなかった。
どうやら、みんな自分の部屋に戻って、それぞれ勉強に励んでいるらしい。そう、僕以外は全員「真面目な訓練生」なのだ。
(しまった……俺だけ明らかに浮いてる……)
さすがにこのまま眠りにつくのは無理だと思い、僕は“あの人”のドアをノックした。
「お~、どうぞ~」
ドアの向こうから聞こえてきたその声は、どこか安心させてくれるトーンだった。
斉(さい)さん――僕が勝手に“精神的な兄貴”だと思っている、頼れる人だ。
「お~、ボンか。どうした?」
と、笑顔で迎えてくれた斉さんの表情に、僕の肩の力がふっと抜けた。
この斉さん、新宿の歌舞伎町でスナックを2軒も経営していたという経歴の持ち主。沖縄出身で、裸一貫で東京に上京し、苦労の末に成功を掴んだ男である。
どこか野生味があり、頼れる雰囲気。冒険好きで、面倒見も良くて、何より絶対に怒らない。そして――ちょっと毛深い。
そんな斉さんには、いつも僕の無謀な話を聞いてもらっていた。
「……実はね」
僕は、今夜の出来事を一つひとつ丁寧に話した。
インポの坪井さんの“あの話”から始まり、ベッキーの部屋でのラブレター事件、そして彼女の旦那が“婦女暴行で3人やっちゃって今服役中”という衝撃的なオチまで――全部、包み隠さず。
話している途中、斉さんは最初は「ふむふむ」と頷いていたが、途中からお腹を抱えて笑い始めた。
「ひっひっひっ……」
「かっかっかっ……」

まるで壊れたエンジンのような笑い声。
いや、こっちは真剣なんですよ! 命がけだったんですよ! ベッキーの旦那に殺されるかもしれなかったんですよ!
……それを、あんた……!
「いやぁ~、ボン、おまえ最高だわ。まじ、映画かドラマかって話だよ、これは!」
くぅ……でも、この笑顔に救われる。悔しいけど、なんかホッとしてしまうのが悔しい。
そして斉さんは、また笑いながら言った。
「でもよ~、ボン。おまえはちゃんと“目上の男”を立ててあげたんだから、立派だよ。感心感心。」
「なにせ、インポの坪井さんを“立てて”あげたんだからよ。はははっ、感謝されるんじゃねぇの?インポ感激~ってな!」
「けっけっけっけっ!」
……。
あぁ、この人、根が悪い(笑)
でも不思議と、僕の中のモヤモヤはすっかり消えていた。
笑われたけど、バカにされた気はしなかった。
むしろ、この話を笑ってくれる人がいるってことに、救われていた。たぶん、誰かに「大丈夫だったな」って言って欲しかったんだ。
ラブレターのことも、ベッキーのことも、全部が全部、思い通りに行ったわけじゃない。でも――そんな夜も、悪くないと思えたのは、斉さんの“毛深い笑顔”のおかげだった。
気がつくと、もう夜中。
斉さんの部屋を出て、廊下に立つと、外からはトレーラーハウス特有の風の音が聞こえてきた。
アメリカの片田舎。
何もない場所。
だけど、ここで僕は一つ、青春の爆発をやらかした。
そしてその証人は――
毛深くて、笑い上戸の、歌舞伎町の元スナックオーナーだった。
続く。
4 responses to “『アメリカの不良娘・ベッキー 』Vol.7――「ラブレターと毛深い男と、夜のトレーラーハウス」――”
-
Wishing you a happy day, every day!
-
Thank you.
-
-
A really good blog and me back again.
-
Thank you very much.
-



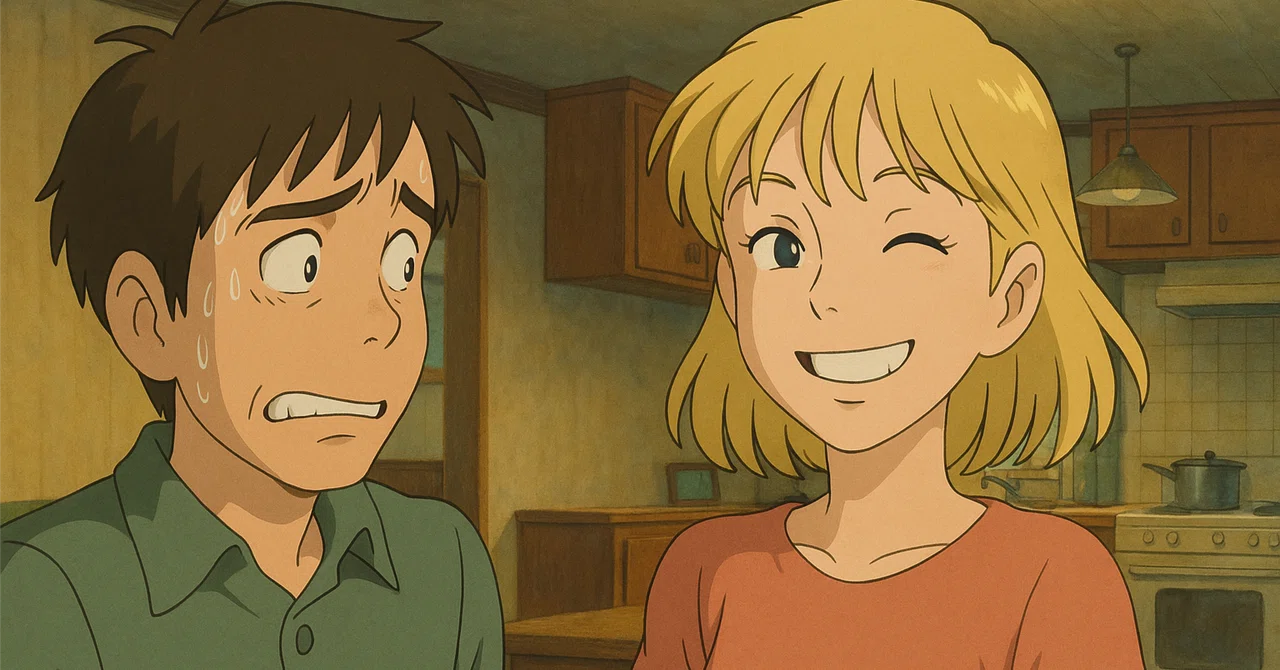



Leave a Reply